先生たちのポートフォリオ
- 6月18日 豊私幼B研修会
-
2016.06.22

- 6月16日 就学前人権教育研究協議会A
-
2016.06.21
「人権尊重の観点に立った就学前教育の今日的課題の解決に向けて」
今回の研修では、人権教育推進の課題や親学習についての理解を深め、子どもたちや保護者への支援、あり方について再認することができました。
私たち保育者は、子どもたちが今求めている支援だけでなく、人格形成に携わる者として、見通しをもった保育・教育をしなければならないと改めて学ぶことができました。
また、人権・差別問題や生命の尊さについて、保育者が日常的に子どもたちに伝え
られるよう、見本となるよう意識していきたいと思いました。
【小川 大阪府教育センター】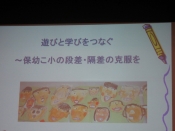
- 6月15日 第2回幼稚園・認定子ども園新規採用教員研修
-
2016.06.21
「子ども理解・保護者理解 ~一人一人を大切に~
「支援教育の在り方と子どもの理解」
今回の研修では、子どもと保護者理解についてや、支援教育の在り方について教えていただきました。子どもや保護者を理解するにあたって、受容、傾聴、共感することで
信頼関係が築かれ、保育現場においては、特に子どもの思いや存在そのものを
「受け止める」ことが大切だと改めて感じました。
また、保育場面で見通しをもたせる工夫や環境構成等、ユニバーサルデザインに
基づく効果的な支援の在り方について学びました。
今後、子どもや保護者と関わる上で、カウンセリングの基本である、共に悩み、共に
考え、共に答えを出すという姿勢を心掛けて、日々保育をしていこうと思います。
【椹 咲州ホール】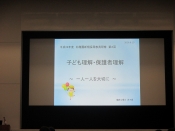
- 6月11日 発達研修
-
2016.06.21
「むずかしい子どもを育てるときに役立つペアレント・トレーニングを学ぼう」
子育てに悩む保護者と子どもがどう関わっていくか、保育者もどう働きかけていくかに
ついて教えていただきました。
保護者の方の心情に寄り添いながら、家庭と幼稚園とで子どもの成長を見守っていけるよう、援助していきたいです。
【高橋 大阪医科大学LDセンター】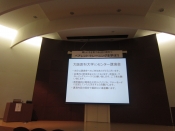
- 6月10日 園内研修
-
2016.06.21
今回の園内研修では、「構成論」について理解
を深めました。「構成論」とは、子どもは知識を教えられて獲得するのではなく、自分で考えることで獲得する、というものです。この理論を踏まえたうえで、普段の子どもの姿を振り返り、この姿の子どもたちはどういった部分が育っているのかを話し合いました。
また、集団ゲームを通して、何が育つのかについても話し合い、実際に園庭に出て、
“めだかの学校” “丸鬼を全員で行いました。
今後も、子どもを見る目を養い、育ちに合った援助をすると共に遊びも充実できるようにしていきたいです。
【高橋 全職員参加】

- 5月28日 発達研修
-
2016.06.07
「発達に課題のある子どもの遊びを通した支援」
今回の研修では、発達に課題のある子どもや、運動に苦手意識がある子どもが楽しく参加できる運動遊びを具体的に知り、また、その遊びが子どもにとってどのような成長に繋がるのかということを学びました。
他にも、床に三角座りで座ることが難しい子どもや、姿勢が悪い子どもに必要な体の使い方なども学びました。
子どもたちは一人ひとり発達が異なります。そんないろいろな子どもがいる中で、みんなが楽しめて成長に繋がるような遊びを今後保育に取り入れて行きたいと思います。
【田中 他7名参加 大阪医科大学】
- 5月21日 園内研修
-
2016.06.07
東豊中幼稚園の教育方針、大切にしていることについて具体的な例を挙げながら、
考えを深めました。「自分で考えて決める力」「自分を大切に思う心」「思いやりをもって人と関わる力」を育てるために、子どもとどう関わっていけばよいのか、子どもの自律性
を育むための保育者のあり方について、全職員で学ぶことができました。
また、子どもの姿の事例を挙げて、その時の保育者のよりよい関わり方をグループにわかれて話し合い、発表しました。
これからも職員同士の話し合いの場を大切に、意見交換したり、協力したりしてよりよい保育をしていきたいと思います。そして、子どもの姿をしっかり見て、一人ひとりに合う援助をしていきたいです。
【山取 他 全職員参加】
- 5月14日 豊私幼 全体研修会
-
2016.05.19
「社会人としての基礎的マナー」
今回の研修では、一年目として私たちが今、取り組むべき基礎的なことを学びました。
日々の挨拶の仕方が身だしなみの大切さ、電話対応や敬語の使い方など、明日に活かせるものばかりでした。
また、他の園の方とディスカッションをする時間もあり、日々の自分の保育への姿勢を振り返り、自分の足りない部分はどこなのか、気づく良い機会になりました。
基礎を身につけ、これからどんどん成長していきたいと思います
【宝珠山 他3名参加 とよなか国際交流センター】
- 5月7日 大私幼 主任研修
-
2016.05.10
『幼児教育って何?」
今回の研修は、テーマのもと、幼児期に大切な経験や考え方、幼児理解の視点を 教育要領にある5領域の理解を深めながら学びました。後半は発達障害ついての
お話を聞かせていただきました。
子どもたちひとりひとりにとって大切な幼児期の保育を担っているという責任の重さを痛感するとともに、様々なことに「なぜ?」という疑問を持ち、日々の保育の質を高められるよう、努力していこうと思います
【 井上 啓子 他3名参加 太閤園 】
- 4月27日 幼稚園新規採用教員研修
-
2016.05.02
講義「大阪府の幼稚園教育」 「幼稚園教育要領と幼児理解」
「新規採用教員研修の受講にあたって」
実践発表 「先輩教員の実践に学ぶ」
今回の研修を通して、保育者の行動や言葉掛けが子どもの成長に大きく関わるということを学びました。その為、日々保育者として働くことに誇りを持ち、考えて行動しなければならないと感じました。
また、子どもたち一人一人の発達の特性に応じた援助ができるように、こどもたちの思いや気持ちを大切にすることが必要だと思いました。
そして、日々の仕事の中でも、先輩の姿を見て学ぶ姿勢を持ち、謙虚な態度で努力することを大切にしていきたいと思います。
【松岡 真央他3名参加 大阪府教育センター】

- 3月31日 合同研修(やまなみ幼稚園と)
-
2016.04.15
「絵本研修」
今回、私たちは絵本についての講義を受け、理解を深めました。日頃、子どもたちと楽しんでいる絵本の歴史や、絵本が与える影響を改めて学ぶことで、もっと子どもたちにたくさんの絵本と出会ってほしいと感じました。
子どもたちの姿に目を向け、様々な経験(実体験)を重ねる中で、今どんな絵本が大切かを見極め、一冊一冊丁寧に読んでいきたいです。
平野 愛 【全員参加 ドーンセンター】
- 3月31日 合同研修(やまなみ幼稚園と)
-
2016.04.15
「マナー研修」
新年度を迎えるにあたり、改めて社会人としてのマナー、挨拶や正しい言葉遣いについて再確認しました。また、今年度目標とすることを全員の前で発表したことで、自分の課題がより明確になりました。
いよいよ新年度が始まります。社会人として正しい態度、言葉遣い、やわらかい表情で、保護者の方や子どもたちと関わっていきたいと思います。
姫島 里佳 【全員参加 ドーンセンター】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅱ 第4分科会
-
2016.04.15
『保育ー幼児教育』の本当に大切なこと
~制度変革のさなかで私たちは何を守り、どう変わるか~
教育研究所 第25次プロジェクト
「カリキュラム」「環境構成」「職員集団の連携」の3グループに分かれて研究の中間発表をしてくださいました。新制度以降の中、各園もそれぞれ多様な保育の状況が生まれており、これまで積み重ねてきた幼稚園の保育の質を保ちながら保育をしていくためには、教職員の研鑽や連携がとても大切だと感じました。
それぞれの発表を聞き、移行の是非の判断は置いておいてもまずは、自園が現在の新しい条件の中におかれた時にどのような課題が生まれ、どのように工夫していくことが大切か、考えていくことの大切さを学びました。
これからもさまざまな側面から保育を学び、努力していきたいです。
瀬戸口 優子 【他1名参加 グランキューブ大阪】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅱ 第6分科会
-
2016.04.14
「発達に課題のある子どもと家族が安心して暮らせるために」
今回の研修では、発達に課題のある子どもとの関わり方や、支援の方法を実際に保育で取り入れた事例をもとに教えていただきました。その中で、支援する前にまずは
その子どもの姿を捉え、気持ちを想像してみることや、子どもをどのように見ていくのか、どのような支援が必要であるのかを見つけることが大切だと学びました。
発達に課題のある子どもが「させられている」と感じないためにも一緒に取り組んでいくことを心がけると共に、一つひとつの喜びを一緒に感じあえる関係を作っていきたいと思います。また、その子どもを取り巻く周りの子どもたちや家族の気持ちにも寄り添いながら、支援していけたらと思いました。
福田 葵 【他11名参加 グランキューブ大阪】

- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ 第5分科会
-
2016.04.14
『生きる』とつながる『食べる』を愉しむ。~
保育のなかの『食べる』の実践~」
ある幼稚園で取り組んでいる食育活動についてお話を聞きました。管理栄養士を雇い、子どもたちが覗けるような給食室で自園調理を行っているそうです。毎朝、農家の方が採れたての野菜を持ってこられるそうで、メニューは野菜、魚で作った和食が中心です。子どもたちは、毎朝届いた野菜を見たり、野菜のことについて栄養士さんに聞いたり、野菜に触れたりするうちに、好んで野菜のおかずをおかわりしに行くようになったそうです。
私たちも子どもたちの苦手意識がなくなったり、食に興味を持ったりできるように給食の時間が楽しいと思える言葉がけや環境を作っていきたいです。
西田 藍 【他9名参加 グランキューブ大阪】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ 第4分科会
-
2016.04.14
「ストロー演奏~音を楽しみ、自分でも作ってみよう~」
この研修では、講師が実際にストローで作った様々なストロー笛を使い、演奏してくださいました。演奏する曲に合わせて仕掛けが違ったストロー笛を使い、演奏してくださったので、見ている私たちは次はどんな仕掛けになっているのか楽しみに見てしまいました。(例:ぞうさんの場合、ストローをつなげて長くした鼻が、ストローを吹くと上下左右に動く。)
実際に私たちも簡単に作ることができるストロー笛を教えていただき、体験することができました。身近なもので簡単に音を楽しむことができると実感しました。ストローだけではなく、他のものでもどんな音が出るのか子どもたちと探し、発見し、音を楽しんでいきたいと思います。
櫻井 友美【他6名参加グランキューブ大阪】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ 第3分科会
-
2016.04.14
「コーチング&アンガーマネジメント」
ビジネスコーチをされている先生に、コーチングとアンガーマネジメントについてお話をいただきました。他園の先生との2人1組での話を『聴き』合うワークショップを通して後輩の先生方の資質を引き出す「コーチング」を学びました。また、怒りの感情と上手に
付き合う「アンガーマネジメント」のお話では、私たちの怒りの正体は、『べき』という
価値観の違いであることを教えていただきました。
今回教えていただいた内容を活かして、より良いコミュニケーションをとり、職員全員で楽しく、良い保育を行えるようにしたいです。
高橋 ちさと 【他4名参加 グランキューブ大阪】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅱ 第2分科会
-
2016.04.14
アレルギー対応「食物アレルギーへの対応~エピペンの使い方~」
今回の研修では、食物アレルギー児への対応の一つの、エピペンの使い方を学びました。実際に練習用のエピペンを使って実践し、学びを深めることができました。
また、アナフィラキシーショックについて、どのような症状か、どういった対応をするのかを改めて知り、アレルギーの大切さを学びました。
実際にエピペンで練習し学ぶことで、1人ひとりがもしもの時に対応できるよう、学んだ情報を共有しあいたいと思います。
山取 彩夏【他9名参加 グランキューブ大阪】
- 3月28日 大研大会 分科会Ⅰ 第1分科会
-
2016.04.14
「私立幼稚園の防災対策について」
「南海トラフ巨大地震について」~地震のメカニズムと防災
南海トラフ大地震が発生した場合に備え、防災マニュアルを作成し、園内研修を通して今までの教育課程を見直し、避難訓練の実践を重
ねてこられた園の防災への取り組みを聴きました。また、大阪府内における想定地震、津波浸水想定区域等も学び、大きな災害に備え、多くの知識を持たねばならないことを痛感しました。
自園で作成した防災マニュアルを基に職員で共有しあい、子どもたちに自分の命を
守る力を育ませることができる避難訓練を実践できるように努めようと思いました。
磯﨑 加奈 【4名参加 グランキューブ大阪】
- 3月28日 大研大会 全体会
-
2016.04.14
「幼児の感情の育ちと大人の関わり~社会性・能動性・自尊心の基礎となるもの~」
感情をコントロールできる思いやりの心をもった子どもを育てるために必要な大人の
関わり方を学びました。子どもたちは幼児期にいろいろなことに興味を持ち、様々な経験をします。そんな大切な時期に、近くにいる大人がたくさん認めて子どもの気持ちに寄り添い、「嬉しかったね。」「悲しいね。」「痛かったんだね。」と、その時々の子どもの
感情を言葉にしてあげることで、”自分は大切な存在なんだ”と思える自尊心が育つのです。
その自尊心があるからこそ、他人と協力できる社会性や、自分で考えて行動できる能動性を育むことができると学びました。これからも、子どもたち一人ひとりの良さをたくさん認めることで自尊心を育み、思いやりの心を持てるよう保育していきたいと思います。
田中 理紗 【全員参加 グランキューブ大阪】


~子育て支援における保育者の課題と役割~
今回の研修を通して、子どもとの関わりは、「自分との関わり・保護者との関わり・
同僚との関わり」全てに共通していると学びました。
子育て支援における保護者とのコミュニケーションと保育者の役割として、保育者全員が同じように関わるのではなく、その中で役割分担することや、保護者の正直な感情を受け止めることも大切だと感じました。
子どもたち一人ひとりと丁寧に関わり、保護者の方に日々の子どもたちの姿を伝える際に、たくさんコミュニケーションをとっていきたいと思います。また、日々の保育を振り返ることも大切にしていきたいです。
【櫻井 他8名参加 豊中人権まちづくりセンターホール】