先生たちのポートフォリオ
- 3月19日 園内研修
-
2016.04.02
- 3月5日 園内研修
-
2016.04.02
今回の園内研修では、各学年やフリーに分かれて、1年間の振り返りをしました。
その中で、来年度に活かせることや、今後保育をする上でのよりよい進め方などを話し合い、各学年やフリーの中で、意見を共有することができました。
次回の園内研修では、今回話し合ったことを全学年で共通理解し、次年度に活かせるよう、話しを進めていきたいと思います。
【谷本 里佳 他24名参加】
- 平成27年度 就学前人権教育研究 協議会C
-
2016.01.19
「第3分科会 子育て支援」
今回の研修では、子育て支援についての実践発表を聞き、4~6名のグループに
分かれて子育て支援について話し合いました。
話を聞いたり、話し合いを通して、子育て支援の場は子育て世代の保護者の繋がりを
つくる、大切な場であることを改めて感じました。そして、これからは保護者のニーズに合わせていろいろな形態で支援を行っていくことが大切であると思いました。
【馬渕 美里 他2名 大阪府教育センター】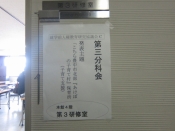

- 1月16日 豊中市私立幼稚園連盟 全体研修会
-
2016.01.19
「子ども主体の協同的な学びを考える
今回の講演では、質の高い保育をするために保育者がどのように子どもと関わることが
大切なのか学びました。質の高い保育は、子どもたちにとって大きな成長に繋がります。
私たち保育者は、子どもの気づきや思いに寄り添い、応じていくことが大切です。また、
それだけでなく一人の学びをクラスのみんなで共有することで協同的な学びとなり、一人
ひとりの意欲や協調性、自己肯定感を培うことに繋がります。
子どもたち一人ひとりと丁寧に関わり、遊びが発展するような環境を整えて、その遊びの
中でたくさんの学びができるよう、保育していきたいと思います。
【田中 理紗 他14名 アクア文化ホール】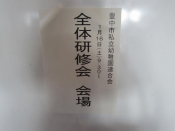

- 12月19、21日 園内研修
-
2015.12.25
副主任が参加した研修の報告を聞き、5~6人に分かれて話し合うグループワークを
行いました。
全職員が子どもたち一人ひとりの育ちを踏まえた上で、保育環境や内容を考え、子どもたちにとってどのような育ちがあるのかという話し合いをすることが保育、教育を学ぶということであると知りました。
「みんなで学び合う」ということが保育や保育者としての質を高めることにおいてとても大切であるということを改めて感じました。
グループワークでは、課題を解決することが目的ではなく、意見や感想を出し合い、聞きあうことを目的として行いました。また、自園の課題を全職員で明確にし、今後どのように取り組んでいくかという土台となるものを話し合いました。
これからも、様々な研修や職員同士での学びあいの場を通して、保育者として互いに
高めあいながら、学び続けたいと思います。そして、そこで共通理解した学びや知識を
活かして保育していきたいと思います。
【谷本 里佳 他 全員参加】

- 12月14日 特定給食講演会Ⅱ
-
2015.12.21
管理栄養士から見た、望ましい給食を継続的に提供するための科学的根拠となる
客観的な指標を知り、自園での給食を見つめ直す機会となりました。
また、アレルギーを持つお子様がいる保護者の気持ちにどのように寄り添い、一緒に
考え、援助・助言ができるのかを学び、考えました。
【篠原 理恵 他1名 大阪府立大学】


- 12月2日 平成27年度 第8回幼稚園新規採用教員研修
-
2015.12.03
「人権について考える ~同和教育の取り組みから学ぶ~」
人権に関する講義と人権博物館の展示観覧をしました。幼少期は、自己肯定感や他人を大切に思う心を持つことが人権意識や人権感覚形成の基礎となることを学びました。
また、保育者が受容・傾聴・共感の姿勢を見せることが子どもの心の扉を開き、信頼関係を築くことにつながり、子どもの思いや理解を深めることが大切だと感じました。
特に、「ありのまま子どもの思いを受け止める」ことを大切に、子どもの思いに気づけるように日々保育をしていこうと思います。
【大野 正恵 他2名参加 大阪人権博物館(リバティおおさか)】
- 11月27日 園内研修
-
2015.12.03
子どもからも保護者からも慕われる保育者を目指してというテーマで園内研修を行い
ました。少人数のグループに分かれて話し合い、意見をまとめ、発表することで、保育者
としての心構えや保育で大切にしていることを再確認できました。
また、子どもの姿の事例を挙げ、職員間で意見交換することによって、子ども理解が
深まり、きめ細やかな保育を実現するための言葉がけや援助の方法を学びました。
全職員で話し合いをすることで、改めてよりよい保育をしようと意識を高めることができました。これからも質の高い保育ができるように努力していきます。
【寄吉 紗奈愛 全員参加】

- 11月7日 豊中市私立幼稚園連盟 B研修
-
2015.11.12
「みんなで考える」ワークショップ ~問題解決の技法を学ぶ~
今回の研修は、6~7人のグループで話し合い、問題を解決していったり自分の意見を
みんなに開示し、グループでの意見を一つにまとめるコンセンサス(合意形成)をしたりと
実践型の研修でした。問題を解決する内容での話し合いでは意見を言うだけではなく、
まとめる、書くなど、役割分担ができていると話が進みやすくなるのだと感じました。
また、みんなの意見をまとめるコンセンサスでは、他の人の意見を聞くことで自分の
考えになかった意見がたくさん出てきて話し合うことでいろいろな意見があることに気づく
ことができました。
話し合いをする中で、自分の意見を言うこと、聞くことの大切さ、また、話をする、聞いて
もらう環境も大切だと思いました。これからもよりよいチームづくりができるよう、年齢問わず意見が言える環境づくりをしていきたいと思います。
【藤田 美陽子 他8名参加】

- 11月7日 豊中市私立幼稚園連盟 A研修
-
2015.11.11
「子どもの育ちからみる造形あそび」
今回の研修では、“造形あそび”について実践を交えながらお話をしていただきました。
子どもたちの育ちに合った造形あそびや環境設定が子どもたちの表現を引き出す重要な
要素であり、それらがいかに大切であるかということを学びました。
実践では、ペーパークラフトや音を聞いて描く線遊びをしたり、コンテパステルで遊んだりもしました。実践を通し、造形遊びの楽しさにも改めて気づくことができました。
今後も、子どもたちと共に楽しみながら取り組んでいきたいです。
【上田 茅波 他10名参加】
- 11月4日 平成27年度 新規採用教員研修(第7回)
-
2015.11.05
「幼児期における食育の重要性」「幼稚園における食育の実践」
「食育」について講義を聞いたり、園で実際に行っている食育の実践を発表で見せて
いただき、食育について深く考えることができました。
幼児期の食育は、生活習慣の基礎や食事のリズム・マナーを身につけることができるので、とても大切だと感じました。まず、保育者が食育に興味を持ち、保育で使える絵本
等を子どもたちに読むことで、少しでも興味を持ってくれるのではないかと思うので、食に
関する絵本を読んでいこうと思いました。
また、他園の先生方とグループになり、園で行っている食育について話を聞くことが
できたので、その取り組みを参考にし、実践できることがあればしていきたいです。
【 櫻井 友美 大阪府教育センター】


- 10月27日 幼保連携認定子ども園 教育・保育要領研修会
-
2015.10.30
【 瀬戸口優子 井上啓子参加 ドーンセンター】

- 10月22日 平成27年度幼稚園・認定子ども園 新規採用教員研修会 秋期全体研修
-
2015.10.23
「幼稚園の先生になって」
他園の先生方体験談を聞かせていただいたり、4~5人のグループに分かれて
お互いの体験談を話し合いました。自分自身の子どもとの関わり方を振り返ることが
でき、仕事の中で得られる達成感や、やりがいがあることをより感じられました。
何より、日々の保育では、事前の準備が大切であるという意見が多く出ました。私も
事前の準備をしっかりとして心に余裕を持ち、保育していきたいです。
【馬渕 美里 他3名 大阪国際交流センター】

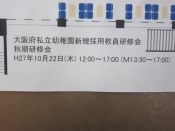
- 10月19日 就学前人権教育研究 協議会B研修
-
2015.10.20
「からだ・ことば・リズム ~ふれあいあそびから~」
ふれあいあそびを実際に体験し、自然と楽しくスキンシップをとることができると学び
ました。
普段うたっている手遊びの手の動きが、字を書いたり、絵を描くための手の動作に
つながっていることがわかりました。たくさんのふれあいあそびを教えていただいたので、
保育に取り入れ、子どもたちと楽しくスキンシップをとっていきたいです。
【櫻井 友美 他2名 大阪府教育センター】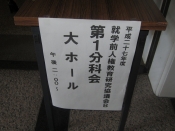

- 9月19日 園内研修
-
2015.09.25
「自律性を育むクッキング」
自律性を育む取り組みの1つとして、クッキング活動を取り入れています。クッキング
活動の特徴とねらいや蒸しパンケーキ、ミックスジュース、白玉だんごなどのレシピの
中で、子どもたちが学ぶ知識について書き出し、発表し合いました。
また、実際にクッキングを始める前の声のかけ方を何人かの先生が行ったり、以前
撮っていたVTRなどを観たりしたことで共通理解が深まったことと思います。
これから行うクッキングでもビデオを撮り、みんなで見直す機会を設け、よりよい
クッキング活動を行うことができるようにしていきたいと思います。
【藤田 美陽子 他22名参加】

- 8月27日 園内研修
-
2015.09.07
「研修報告 等」
夏休み中に職員それぞれが参加した研修内容を報告しあいました。共有しておきたいこと、今後の保育で活かせそうなことを伝え合う場を持つことで、それぞれが夏の研修を
振り返って整理し、まとめるという作業の中、理解が深まったように思います。
2学期の行事について見直しを行いました。ひとつひとつの意味や必要性を話し合い、
より充実した保育を志しています。
【井上 啓子 他22名参加】
- 8月25日 園内研修
-
2015.09.07
「教育課程について」
前回の園内研修に引き続き、教育課程について話し合いを行いました。2学期からも
子どもの姿や育ちを個々に合わせ、しっかりと見ることができるよう、学年ごとのねらいや
保育内容等を改めて考える貴重な時間となりました。
子どもたちが充分に遊べるように、また、危険等がないよう保育室や園庭の環境設定をしました。
【篠原 理恵 他22名参加】
- 9月2日 第6回幼稚園新規採用教員研修
-
2015.09.03
「保護者理解 ~家庭との連携の観点から~」
「親学習」を実際に体験してみて、「親の立場」で物事を考えてみることで、よりよい
保育に繋げたいと思いました。
【馬渕 美里 大阪府教育センター】
- 9月2日 第6回幼稚園新規採用教員研修
-
2015.09.03
「児童虐待の現状と課題」
児童虐待についての講演を聞いて、児童虐待を防ぐために私たち保育者ができることは多くあると感じました日々の保護者や、子どもとの関わりをより大事にしようと思いました。
【馬渕 美里 大阪府教育センター】
- 8月7日 フレーベル研 第2日目
-
2015.08.31
「絵本が身近にある生活」
絵本の朗読では、とても心がこもった読み方をされていて、言葉がすっと
体の中に入って行く感じがしました。きっと何度も下読みをされて、また、絵本の
良さを伝えたいという思いが強くあるからだと思います。
下読みをしっかりとして、伝えたいことは何か考えながら読み聞かせをして
いきたいと思います。
【小幡 紗希 他5名参加 京都テルサ】


これからも3歳、4歳、5歳児の成長を見通し、縦のつながりも大切にした保育をしていきたいです。職員全員が一つのチームとしてより良い保育ができるよう努めてまいりたいと思います。
【目黒絵梨奈 他24名参加】